
・X-H2ってどんなカメラ?
・外観や使い心地は?
・どんな写真が撮れる?
こんな疑問をお持ちのあなたへ。
こちらの記事では富士フイルムの高画素フラッグシップ機であるX-H2についての詳細なレビューをまとめています。
カメラのスペックや外観、使用感やおすすめポイントまでを作例とともにまとめているので、この記事1本でX-H2の写真性能がほとんど分かるようになっております。
記事を読み進めるとX-H2が欲しくなっちゃうかもですので、最後まで読まれる方は自己責任でご覧ください。
X-H2はこんな人にオススメ!
- コスパに優れた高機能カメラが欲しい人
- 富士フイルム最高性能のカメラが必要な人
- 大きなレンズで画質を優先した写真を撮りたい人

そーいち
- FUJIFILMのカメラを愛用&大好き
- 関西の観光地での写真を撮ることが趣味
- カメラの気になる疑問を解決するブログをやってます
仕様

こちらの項目では富士フイルムの高画素フラッグシップ機であるX-H2についてのスペックと概要についてまとめました。
| X-H2 主な仕様 | |
|---|---|
| レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
| 撮像素子 | APS-C |
| 有効画素数 | 約4,020万画素 |
| 画像処理エンジン | X-Processor 5 |
| ファインダー | 0.5型有機ELファインダー 約576万ドット |
| サイズ | 幅: 136.3mm 高さ: 92.9mm 奥行き: 84.6mm |
| 重さ | 約660g(バッテリー、メモリカードあり) |
| 詳しい仕様表 | こちら |
カメラは仕様が多いので、詳しい仕様が気になる方は公式ホームページの仕様表をご覧ください。
カメラの概要
X-H2はプロが使用することを想定して作られたカメラです。
後述する特徴をみれば一目瞭然ですが、プロ現場での使用を想定したであろうスペックが盛りだくさんです。
だからといってプロだけが使うカメラかというとそうでもなく、ハイアマチュアや富士フイルムの大口径レンズ好きのニーズも満たす設計、仕様になっています。
こちらのカメラは富士フイルムのフラッグシップという位置付けです。しかし、他社カメラのフラッグシップと比べると比較的手の届きやすい価格設定なのも魅力の一つ。
そんなコスパに優れた高スペックカメラの特徴を下の項目でまとめました。

X-H2の特徴【画質】

こちらの項目ではX-H2の進化した画質性能についてまとめました。
約4,020万画素の新型センサー
X-H2最大の特徴である「新型高画素センサー」が採用されたことにより、富士フイルムのレンズ性能を最大限に引き出すことのできるカメラが誕生しました。
Xシリーズ初の約4,020万画素を誇るセンサーを搭載。今までのセンサー性能から改善されたことにより、APS-Cの小型なセンサーにも関わらずノイズの少ない写りをするカメラです。
高画素センサーを採用することにより、今まで以上に高精細な写真を撮ることができるようになりました。
露出の自由度が上がるISO125スタート
APS-Cのカメラはフルサイズと比べるとセンサーが小さいです。なので高画素センサーにすると一画素に入る光が減ってしまうのでノイズの少ない画質をキープするのは難しいとされています。
なので高画素機はノイズが出やすいが、開発者さんが猛烈に性能を追い込んでくれたおかげで2,600万画素のセンサーとほぼ同じノイズレベルにまでなりました。
高画素はノイズが発生しやすいというデメリットがありますが、このカメラに限っては高画素でも気にならないノイズレベルで写真が撮れます。
新たなフィルムシミュレーション搭載
このカメラに限ったことではありませんが、富士フイルムのフィルムシミュレーションは、撮って出しで最高の絵が出せることをコンセプトに作られています。
富士フイルムが約80年培ってきた色再現のノウハウがここでも存分に発揮されています。
フィルムシミュレーションは約80年の歴史の中で世界が認めた色をデジタルで再現しているので、カメラを始めたばかりの方やパソコンをお持ちでない方でも、難しい操作は一切なくお手軽に綺麗な色味で写真を撮ることができます。
加えて、X-H2には新しいフィルムシミュレーションの「ノスタルジックネガ」が追加されています。
撮って出し派の人にとっては色表現の幅が広がることは大きなメリットですね。


フィルムシミュレーション比較 / 左 : 標準のPROVIA(プロビア) / 右 : 新しく追加されたNOSTALGIC Neg(ノスタルジックネガ)
その他進化した画質
- 1/180,000のシャッタースピード
- 8K30pの動画性能
- 8Kオーバーサンプリング4K
- 160MPのピクセルマルチシフト
X-H2はプロが使用する現場を想定して作られたフラッグシップ機なので、最新機能がてんこ盛りです。
しかし、そのほとんどはかなりの特殊用途なので趣味の写真に使う分には特に必要ではないのでこの辺りの説明は割愛。
X-H2の特徴【機能】

画質性能に引き続き、こちらでは機能面の新機能をご紹介。
AF性能がめっちゃ良くなった
オートフォーカスの性能は以前のシリーズと比べて格段に良くなりました。
正確で高速になったAF
X-H2のAFが格段に良くなった理由は「被写体検出AI」です。色んなレビューを見ていても、旧型よりAFが進化したのは明らか。
さらに、AFの検出精度も上がっているので被写体を粘り強くトラッキングしてくれます。
以前、筆者は公園で子どもの撮影を依頼されたことがありまして、その時にはX-H2を使用。公園で子どもが元気よく動き回っていましたが、瞳をしっかりと認識して正確にピントを合わせてくれました。
子どもが後ろから前へと迫ってくるシーンに限り、ピントが後ろへ抜けるケースがありましたが、それ以外は問題なし。子どもや犬猫の撮影なら難なくこなしてくれます。
被写体検出できるものが増えた
被写体検出できる数が圧倒的に増えました。X-H2が検出できる被写体は以下の通り。
- 人物
- 動物
- 鳥
- 車
- バイク&自転車
- 飛行機
- 電車
- 昆虫←New
- ドローン←New
X-H2の被写体検出は一般消費者の使用シーンのほぼ全てに自動でフォーカスを合わせてくれるので、撮影がとっても楽になります。
フォーカスの精度と速度がパワーアップしたことで、今まで以上に撮影に集中できるカメラとなりました。
フォーカスはカメラ任せで絵作りに神経を注げるようになったのはX-H2を選ぶ大きなメリットです。
※Newはアップデートで検出可能になった被写体です。
デジタルテレコン←これ重要
新型高画素センサーを搭載したことにより、デジタルテレコン機能が追加されました。
テレコンとは、望遠レンズのマウント部分に繋ぐアダプターのこと。これをつけると1.4倍、2倍の焦点距離で撮影することができます。
これのデジタル版がデジタルテレコン。ボタンひとつで焦点距離の1.4倍と2倍で撮影できるようになりました。若干画質は落ちるものの、元々約4,020万画素あるカメラなので、画素が半分でも約2,010万画素は残ることになります。


撮影時にもうちょっと寄りたいなと思った時に、ボタンひとつでズームしたかのように撮影できます。撮って出しで写真をサクッとシェアしたい方にぴったりの機能が搭載。
この機能は高画素機のX-H2,X-T5にしか搭載されていない機能です。
これが大変便利。たとえば、単焦点レンズのXF16mm F1.4R WRをデジタルテレコンでつかうと、フルサイズ換算で24-48mmの画角になります。
また、小三元ズームのXF16-80mm F4 R OIS WRならばフルサイズ換算で24-244mmのズームレンズとして使用できます。
撮って出しのみの機能ですが、旅行などの荷物を減らしたい時にとっても重宝するのです!
7段分の手ぶれ補正で手ブレ知らず
今やほとんどのミラーレスカメラに手ぶれ補正が入るようになりました。
そんな中でも他社メーカーの最高水準に匹敵する7段分の手ぶれ補正がX-H2には搭載されています。
レンズのF値を絞り込みたい場合や暗いシーンでも手ぶれを気にせず撮影できるのは、ユーザーにとってありがたい仕様です。
その他進化した機能
びっくりするくらい高画質なファインダー
ファインダーは約576万ドットと、高精細なファインダーが搭載されました。他社フルサイズ機で同価格帯カメラのほとんどは300万ドット代なので、コスパがいいですね。
防塵防滴でより丈夫に
カメラが防塵防滴だと、雨などで故障するリスクが格段に減るので天候を気にせず撮影しやすくなります。
CFexpress タイプBカードに対応
通常の写真撮影に関してはSDカードで十分ですが、CFexpressの方が動作が速いのでこれも嬉しいポイント。
外観

外観デザインは、高級感のある雰囲気。他社のハイアマチュア以上のカメラと同様に握りやすい大きめのグリップ、ボタン類の多さ、モードダイヤルなど、使い心地を重視したデザインになっています。
富士フイルムのカメラはフィルムカメラのデザインに寄せたものが多い中、現代的なカメラへの挑戦ともいえるシリーズです。
他のカメラシリーズと異なるのは天面のサブ液晶モニター。このモニターでは露出の設定やフィルムシュミレーションなどの設定が上部から確認できる仕様です。
また、電源オフ時には撮影可能枚数とバッテリー残量を表示してくれます。なので電源をつけることなくカード内のデータ整理の有無、バッテリー残量の確認ができるため、確認のためにわざわざ電源を入れる手間も省けます。
使用感

こちらではX-H2の使用感について特徴的な4つの項目でまとめました。
グリップの握り心地
フルサイズ機に代表されるような深いグリップが採用されているので、大きなレンズでもしっかりとカメラを支えて撮影することができます。
最近の富士フイルムのレンズは解像度をアップするべく、旧型と比べてレンズが大きく重くなっています。X-H2は高画素センサーを積んでおり、そのような高解像なレンズの仕様が想定されるためグリップの握り心地は非常に重要です。
筆者は元々グリップの深いSONYのα7ivを仕様していました。それから比べると、遜色のない使い心地なので違和感なく移行することができました。
開放F1.4以下の大口径レンズがお好きな方はグリップの浅い機種よりもX-H2の方が断然使い心地が良いです。
バリアングル液晶がありがたい

今やミラーレスカメラの定番となったバリアングル液晶。ミラーレスはファインダーより液晶モニターを見て撮影することが多い分、チルト液晶よりも自由度の高いバリアングルが人気です。
実際に使用していてもバリアングルの方がいろんな撮影シーンに対して汎用性が高く撮影の自由度が増します。
カスタムダイヤルが豊富

モードダイヤルにあるカスタム数は合計で7個と数が多く使い勝手が非常にいいです。
富士フイルムは「撮って出しで最高の絵が出る」という思想のもとカメラを設計しています。そこで重要になってくるのがフィルムシミュレーションをはじめとする色と露出の制御。
富士フイルムのカメラにしかないメリットは写真をカメラ内の現像処理で細かく調節できること。
例えばフィルムシミュレーションに対してシャドーを締める、シャープネスを緩める、肌だけを検出して滑らかにするなど、さまざまな調節を行えます。さらには、富士フイルムのアプリ『FujiXWeekly』では世界的なフィルムメーカーKodakの色味を再現したレシピや富士フイルムの過去のフィルムを再現した現像のデータの公開がされています。
つまり富士フイルムのカメラはカメラ一つで豊富な色表現ができる機能と仕組みがあり、富士フイルムにしかない価値ともいえます。
その調節をカスタムボタンに設定して、撮影したと同時に好みの写真や作風に仕上げることができるので、カスタムボタンが多いと最大7つの現像データを保存することができるのです。
好みの色再現を7つも設定できるX-H2は撮って出しでも楽しめる幅が広いカメラです。
予備バッテリーはあったほうがいい
X-H2を旅行やスナップなどの外で使用するのであれば予備バッテリーは必須です。
筆者は旅行やスナップで使用することが多いのですが、観光名所で2~3時間ガッツリ写真を撮るとバッテリーが切れそうになることが多くありました。
電池がないから撮影を控えようなんてなればせっかくのシャッターチャンスを逃してしまうことに、、、
なので野外で長時間の撮影で使用される場合は富士フイルムの純正バッテリーのNP-W235を手に入れましょう。
X-H2のデメリット

前述したレビューではメリットばかりになるので、筆者が体感したデメリットを3つの項目でまとめておきます。
データが重い
高画素機ということもあり、データが大きくなることには覚悟が必要です。
X-H2はRAWで撮影した場合、写真一枚のデータ量はおおよそ85MBでした。これを一般的なSDカードの企画で考えるとRAWで撮影した場合は
- 1GB=約12枚
- 32GB=約385枚
- 64GB=約771枚
- 128GB=約1,542枚
となります。
X-H2を旅行や子供の写真など、たくさんパシャパシャ撮りたくなるシーンと想定すると、最低でも64GBのSDカードがある方がいいですね。
筆者は128GB以上で使用していますが、それくらいのSDカードであればデータ残量を気にすることなく撮影ができます。
※jpegのみの記録であれば32GBでも問題ない程度です。
ダブルスロットだがCF express type BとSDカードが別々でしか使えない
フラッグシップ機ということもあり、記録メディアがダブルスロットなのは大歓迎だが、それぞれで記録メディアが異なるのでSDしかない人にとってはシングルスロットと変わらない使い勝手になってしまいます。
SONYのα7ivならばスロット1はCF expressとSDカードの2種類を選択できるため、SDカード2枚でダブルスロットが使えます。
しかし、X-H2はスロット1がCF express、スロット2がSDカードしか使えません。
今後のX-Hシリーズもα7ivのようになることを願うばかりだが、今回は妥協するしかなさそうです。
とはいえど、バックアップとしてダブルスロットを使用するのは撮り直しのできないプロの現場くらいです。一般ユーザーの趣味用途でしたらSDカード1枚で十分使用できます。
露出を瞬時に調整できるダイヤルが2つしかない
X-Hシリーズのダイヤルはグリップの部分と軍艦部分の合計2個しかないので、マニュアルモードの場合はカメラ側で3つの露出をコントロールすることができません。
写真における露出はシャッタースピード、F値、ISOの3つがあり、ユーザーとしては直感的かつ瞬時に3つの露出をコントロールしたいというのが本音。
可能であれば、今後SONYのα7ivのように豊富なダイヤル数になることが望ましいです。(α7ivは4個もあるので露出とホワイトバランスをカメラ側で瞬時に調節できます)
現状の解決策としては、レンズの絞りリングでF値を操作して、シャッタースピードとISOをカメラ側のダイヤルで操作するのが最適解。
上記3つが改善されればより使いやすいカメラになるでしょう。
作例
こちらではX-H2のカメラを仕様して撮影した作例写真をご紹介。
写真をタップしていただくと、Flickrという海外の写真共有サイトへつながります。ブログでは画質に制限があるものの、Flickrでは高画質な作例をお楽しみいただけます。
さらに、写真撮影時のF値やシャッタースピードなどのEXIF情報も見ることができるので、ぜひ参考にしてみてください。














まとめ
最後にX-H2を手に入れるべき理由についてまとめました。
X-H2を手に入れるべき最大の理由
今回の濃厚レビュー記事を見ても分かる通り、X-H2は富士フイルムがかなりの力を注いで作り上げた高画素フラッグシップ機です。
そんな高スペック機を手に入れるべき最大の理由は『中古市場においてコスパが良すぎる』ことです。
昨今の富士フイルムはX-T5やX-S20の人気が高く、メーカーの予想を大幅に上回るオーダーが入っていて、それが原因で受注を停止する事態となっております。
中古市場にもほとんど在庫がなく、今や手に入らないカメラとなってしまいました。
対して今回ご紹介のX-H2は新品中古ともに在庫があり、ちゃんと手に入るカメラなのです。
富士フイルムのカメラの中でもかなりの高スペック機なのに、中古市場は在庫が多いので値段も安定して購入できます。
中古市場の在庫が多いということは人気がないのでは?と思われる方もいるでしょう。
これは富士フイルムを欲するユーザーの多くがよりコンパクトでクラシックなカメラを求めていることが理由なのではないかと思います。
今回のX-H2はその人気要素であるクラシック感を取り入れたカメラではないので、それを期待したユーザーが売っちゃって、中古市場が潤沢になったのかと推測しています。
そのおかげで最高水準のカメラがコスパよく手に入れることができます。筆者はそのチャンスを掴めたユーザーの一人で、高性能なカメラをコスパよく手に入れられたので大変満足しております。
今や入手困難になってしまった富士フイルムのカメラの中で、最高レベルの高性能カメラなのに他機種よりも手に入りやすくコスパのいいX-H2。
・コスパに優れた高機能カメラが欲しい
・富士フイルム最高性能のカメラが必要
・大きなレンズで画質を優先した写真を撮りたい
そんなあなたはぜひ高性能なX-H2を手にいれてカメラライフを楽しんで下さい。

X-H2Sのことはよく分かったけど、高画素機のX-H2と比較したらどうなんだろう?
こんなふうに疑問を持つあなたへ。
X-H2とX-H2Sのが画質や高感度ノイズの比較してみたので、こちらもあわせてご覧ください。


X-H2の長期レビュー
X-H2を半年間ガッツリ使用した長期レビューもございます。今回の記事とは違い、長期間使用した率直な感想や使い心地をご紹介しております。


機材をお得に買う方法


記事を読んで気になったカメラやレンズ。せっかくならお得に購入したいはず。そんな方のためにお得に機材を手にいれる方法をご紹介いたします。
富士フイルムの公式オンラインストア『フジフイルムモール』は初回10%OFFで購入できるんです。しかも、期間中なら何度でも使えるので2回目以降も10%OFFです。
フジフイルムモールで購入すると他にもいいこといっぱいなのでまとめました。
- 初回限定10%OFF
- 5,000円以上で送料無料
- あんしんの長期3年保証
- 最長60回まで分割手数料が無料
- 12:00までの注文で当日出荷
ハイ、めっちゃお得です。ちなみにこれらのサービスはフジフイルムメンバーズに新規会員登録することで利用できます。
フジフイルムモール
上のリンクからでもフジフイルムモールへ飛ぶことができます。こちらの公式サイトで商品を検索して現在の価格などを確かめてみて下さい。
他にもアマゾン、楽天、ヤフーショッピングで購入できます。人によってはポイントを貯めたいなんて方のためにコチラもリンクを貼っておきます。
FUJIFILMに関するほかの記事
当ブログでは、今回のようにFUJIFILMのカメラに関する記事がたくさんございます。
FUJIFILMのことが好きな人や、どんなカメラか気になっている人はぜひほかの記事も見てみてください。
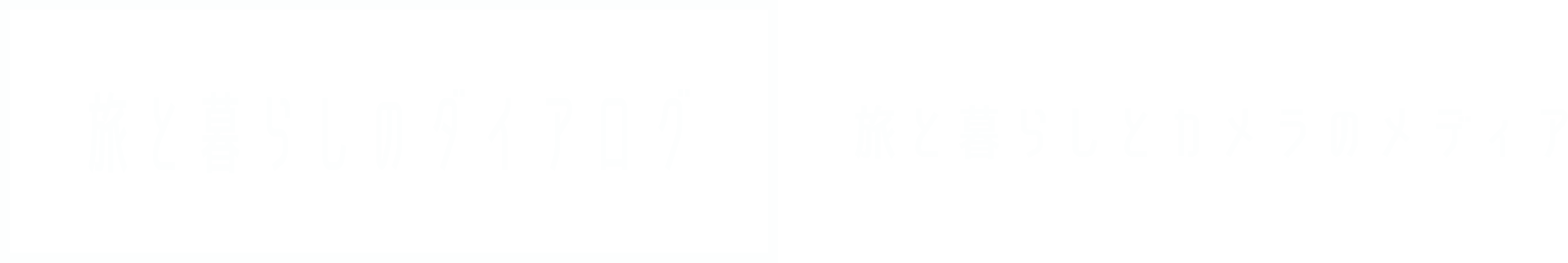










コメント